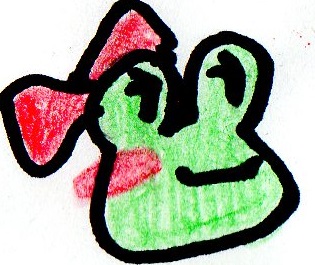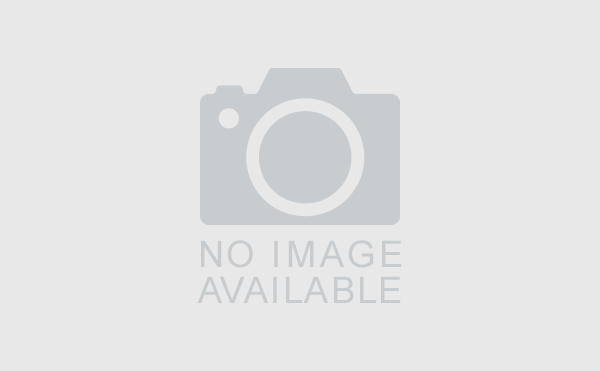【化学基礎】物質量モル(mol)の意味をわかりやすく解説!高校化学ではこう教えるしかない!高校生はもちろん!若手教員・教師は指導案に!
ココケロくん
相対質量・・原子量・・仮の重さって意味わからん・・・
ココミちゃん
そうねえ・・やっぱりg[グラム]の方が使いやすいもんね
ココケロくん
原子1個1個が軽すぎてな・・一体何個集めたら現実的な重さになるのやら
ココミちゃん
ココミロくん!それよ!!!
実は、2019年に物質量モル(mol)の定義は変更されています。
以下のPDF「キログラムとモルの新しい定義 ―キログラム原器から物理定数へ―」はすこぶる難しいので読まなくてもいいですが、一応経緯を置いておきます。ヘッダー画像がPDFに出てくる「キログラム原器」です。
https://www.jsac.or.jp/bunseki/pdf/bunseki2019/201905p193.pdf
歴史的にもmol概念はかなーり難しいため、高校生も教える側の教員も物質量モルは苦手になりがちです。
化学基礎も化学もmolからは逃げられないというのに・・・!!!!
しかし、嘆いても仕方ない!我々は生き延びなければならない!
ここからは、長い経験の中で、高校生に物質量モル(mol)を教えるにはこの流れしかない、という究極の流れをお教えします。
高校生の皆さんは勉強のために、教員の皆さんは指導案作りや板書作りにお役立てください。
物質量を”受け入れる”流れはおそらくこれしかない
原子は軽すぎて質量が扱いづらい
↓
相対質量の導入
↓
同位体おるやんけ!!!
↓
原子量の導入
ここまでが
こちらに書いた内容になります。
続きとして
原子量の導入
↓
仮の重さ(相対質量とその平均としての原子量)と実際の重さ(g)を繋げたいなあ
↓
物質量モル(mol)の導入
となります。では、参りましょう!
原子量を導入したけど、仮の質量って・・ねえ?
例えば塩素Clの原子量は35.5とされることが多いです。
で、この35.5というのは相対質量の平均値なので、結局は相対質量。
でも質量って、実際は「g」(グラム)で運用されるのが普通ですよね。
相対質量やら原子量やら言われても・・現実で使えないと・・ってなっちゃいます。
そこで人類は考えました。
塩素Clの原子量は35.5
じゃあ実際に塩素Clが35.5 [g] になるのはどんな時なのか?
結果、塩素Clが35.5[g] すなわち原子量に[g]を付けた値になるのは、
6.0×1023 [個]だったのです。
これこそが1.0[mol]が6.0×1023 [個]である理由そのもの。
この数を集めることで、仮の数値だった原子量が実際の数値である質量へと変換されるのです。
だからmol計算ではこうなる
(1)1.0[mol]は6.0×1023 [個]なので、これを用いてmolと個数の変換をしましょう。
となります。これが教科書の最初の問題。
(2)1.0[mol]は|原子量・分子量・式量《モル質量》に[g]をつけたものなので、これを用いてmolとgの変換をしましょう。
と次になります。少し難しい話ですが、Clは原子量35.5、Hは1.0です。
これは相対質量であるため、Clの35.5分の1の重さがHです。
ここで、Clを1.0[mol]集めると原子量gになるのでClは35.5[g]です。
そしてClの35.5分の1の重さがHですので、Hは1.0[g]
すなわちHも原子量1.0に[g]を付けた数値となり、全ての原子量を同様に使うことが出来ます。
便利!!!!!!
その他、(3)標準状態の気体の体積とmol の話や(4)密度処理の話に繋がっていきます。
これはまた次回のnoteにて、たくさんの計算問題を通して確認していきましょう。
ではまた!
※noteに好きボタン押してくれたら更新早くなります。
そういうわかりやすい人間なので・・・。フォローもしてね。
なお、Xアカウントもあります。貼っておくのでこちらもフォローお願いします。
見たらわかるように作り立てホヤホヤ。
今からフォローしたら古参になれます。
ココミロかんりにん(@kokomiroseibutu)さん / X